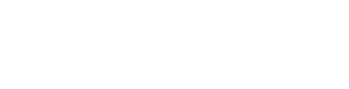小型水草水槽を立ち上げてみよう! ということで、当ブログAquaTurtliumでは「小型水草水槽立ち上げ記録」というタイトルで立ち上げの様子をまとめています。
今回はそんな小型水草水槽立ち上げシリーズ第1回「水槽選定とセッティング」に続きまして、第2回「フィルターの選定と能力向上」という内容になっています。小型水槽や水草水槽の立ち上げを考えている方は、ぜひ参考にしてみて下さいね。
連載「小型水草水槽の作り方」
- 小型水草水槽の立ち上げ!水槽の選び方とセッティング方法を解説!
- 小型水槽におすすめ!外掛け式フィルター改造で濾過能力向上
- 水草水槽には欠かせない!発酵式でCO2を添加する方法
- 小型水草水槽の立ち上げ!購入する水草の種類を決める方法
- 小型水草水槽の立ち上げ!設置場所からろ過までコレで完璧!
ということで今回はシリーズ第2回としてフィルターについて考えていきます。記事タイトルを読めば分かってしまうんですが、今回はフィルターとして外掛けフィルターを選択しました。そしてさらに、それを改造していきます!
今回の記事では、何故ろ過フィルターとして外掛け式フィルターを選び、更にそれを改造して使用する事にしたのかということと、外掛け式フィルター改造の具体的な手順を紹介します。
フィルターの選定
まずは当然ながら使用するフィルター(濾過器)を決めなければなりません。フィルターには様々な種類があり、それぞれに長所や短所があるので目的に応じた選択が必要になります。各フィルターの特徴や選び方は以下の記事に詳しくまとめてあります。
-

-
水槽用ろ過フィルターの選び方と外部・底面など種類別おすすめ製品
熱帯魚、金魚、亀等を飼育するアクアリウムで必要になる水槽用のろ過装置を解説します。外部フィルター、底面フィルター等のろ過フィルター別の長所・短所・適合水槽や、ろ過の原理、ろ過フィルターの種類、ろ材についてもまとめます。
興味がある方はぜひ読んで下さいね。当ブログの中でもかなりの人気記事で、アクアリウムの初心者にはかなり役立つと思います。
今回は各フィルターの長所・短所を目的に応じて吟味した結果、外掛け式フィルターを使うことにしました。
外掛け式フィルターを使うことにしたので手頃なやつを探してきます。今回は引越しの時に使ったコトブキのプロフィットフィルター F2が余っていたのでこれを使うことにしました。水槽のサイズ的にも問題なさそうです。
プロフィットフィルター F2は既に廃盤となっている商品で、現在は後継機としてプロフィットフィルター X2が販売されています。マグネットポンプが水中ポンプに変更されています。個人的にはマグネットポンプを使っている旧型のF2の方が好きです。
フィルターの改造
では以下でこのフィルターを改造していきます。今回は市販品を改造して使用する事になるので、どういった目的で改造するのかということを良く理解するようにして下さい。そうしないと、せっかく改造しても効果の無い使い方をしてしまうこともあります。改造の作業自体はとても簡単なので、説明通りにやれば大丈夫です。
改造の目的
外掛け式フィルターの改造目的は、生物濾過を有効に機能させることです。
外掛け式として販売されているほとんどのフィルターは、活性炭などを濾材とし、メインとなる濾過方法は吸着濾過です。それを改造して生物濾過として機能させるためには、生物濾過用の濾材を入れることができ、かつ有効に生物濾過が働くよう流路が長くなるように濾過槽を改造することが有効であると考えられます。
-

-
生物濾過と硝化バクテリアの働きまとめ!アクアリウム水槽管理の基礎
アクアリウムや水生生物の飼育で非常に重要な「生物ろ過」について解説します。生物濾過とは、バクテリア(細菌)の働きにより、水中の有機物が腐って生じる有毒物質(アンモニア)を毒性の低い物質(硝酸塩)に分解することを指します。これより水換え頻度を減らすことが可能です。
以下ではこの方針に従って改造していきます。
パーツの準備

用意した材料は以下の通りです。
- 鉢底ネット
- 猫よけマット
- プラスチックの板
ダイソーのような100円均一ショップか、ホームセンターに行けばこの材料は揃えることができます。それぞれのパーツを切ったり曲げたりと加工していますが、詳細については以下の作業工程の説明と一緒に書きます。
ポンプカバー

鉢底ネットを適当な大きさにカットして折り曲げ、パイプが通る穴をあけてポンプカバーを作ります。

こんな感じで設置。ポンプ周辺で抵抗が大きくなって極端に水流が弱くなることを防ぎます。
仕切り板①

手前側(ポンプ周辺)と奥側を分離して流路の長さを稼ぐために仕切り板(画像中央の白い板)を指し込みます。私は、以前ミスト風バックスクリーンを自作した際に余った「PPクラフトシート」を使いましたが、プラスチックの板なら多分何でもいいと思います。左上の部分は水の流れ道を作るため切り欠いています。
-

-
半透明の背景で明るい水槽!ミスト風バックスクリーンの自作
水槽の背景を半透明にすると明るい雰囲気と開放感を保ちつつ水槽背後を見えなくすることができます。そんな理想を実現するミスト風バックスクリーンの作り方を紹介します。ネイチャーアクアリウム水槽におすすめのバックスクリーンです。
すのこ
仕切り板の切り欠き部分を通って濾過槽を移動した水は、一度下方向に進んでから上の排水口から水槽内に戻ります。水を下方向に進ませるために、下部の通水を良くするすのこを設置します。

適当なサイズにカットして、突起を多少カットした猫よけマットの上に同サイズの鉢底ネットを載せればすのこの完成です。

実際にフィルター内に設置するとこんな感じになります。
仕切り板②

すのこと同様に、水の流れを下に向けるための仕切り板を設置します。材料は仕切り板①と同じです。フィルターの左右の壁面が垂直ではなくやや斜めになっているので、隙間ができないように斜めにカットして、元からあった溝に差し込みました。
水流抑制板

フィルターから水槽へ戻る水の勢いが強くなりすぎるので、水流を弱めるための板を設置します。鉢底ネットをカットしたものを折り曲げてフィルターの排水口に設置し、フィルターから水槽へ戻る水が必ず鉢底ネットを通るようにします。この鉢底ネットの板のおかげで水流を多少弱めることができます。
濾材の投入

ポンプ周辺には物理濾過用のウールマット、その後に生物濾過用のスポンジ濾材を入れます。このスポンジ濾材は洗車スポンジを利用して自作したものです。購入するとかなり高くつくこともある濾材ですが、自作してしまえば数百円で10リットル以上の量を作ることが出来ます。
-

-
自作でコストダウン!スポンジ濾材と濾材ネットの自作方法
購入すると高価なアクアリウム用品である「濾材」を自作して安価に入手する方法とろ材用ネットの作り方を紹介します。ポリエーテル製の洗車スポンジにより高性能な濾材を手軽に作ることができ、安定した熱帯魚やエビ飼育を実現できます。
詳しい方法はこちらの記事で紹介しています。簡単にまとめると洗車スポンジを1cm角の大きさに切るというだけなのですが、ポリエーテルなどの水に溶けにくい素材の洗車スポンジを使うのがポイントです。

後ろから見るとこんな感じになります。
完成

フィルターに蓋をしたら完成です! フィルター内部の水の流れは画像の水色の矢印のようになります。


フィルター内を回り道をするように水が流れることで濾材と水が触れ合う面積が大きくなり、濾過能力の向上が期待できます!
注意点
2014/10/14 追記
濾過能力が向上して良いこと尽くめのように思われる外掛け式フィルターの改造ですが、セッティングがマズイと藍藻などのコケ発生の原因となってしまう可能性があります。下の記事は実際に私の水槽で、改造した外掛け式フィルターに藍藻が発生してしまった様子とその対処法を紹介している記事です。
-

-
藍藻の発生源を特定!原因は改造した外掛け式フィルター!?
水草水槽の大敵・藍藻ですが、生物濾過仕様に改造した外掛け式フィルターがその原因となる可能性があります。想定外の使用法なので水流低下や遮光不足が藍藻等のコケ発生の原因となりえます。実際の藍藻発生事例と対策方法を紹介します。
濾過能力を高くしたいと思って濾材を詰め込み過ぎると水流が弱まってコケが発生しやすくなりますし、外掛け式フィルターは外部フィルターなどと比べてもともと遮光性が高くないのでさらにコケが発生しやすい環境になります。あまり濾材を詰め込みすぎず、光もなるべく当たらないように使用するのが良いと思います。
まとめ
今回はプロフィットフィルター F2を生物濾過装置に改造してみました。参考になったでしょうか?
プロフィットフィルター F2以外の外掛けフィルターも、同様の方法で生物濾過をバッチリ効かせたフィルターに改造することができると思います! ただし、あくまでも小型の外掛け式フィルターなので強力な濾過能力とまではいきません。大きなサイズの水槽や過密水槽の場合にはより強力な濾過能力をもつフィルターを導入した方が賢明だと思います。
なお、今回の記事の作成にあたり以下のサイトを参考にさせていただきました。ありがとうございました。
参考コトブキ「プロフィットフィルターF2」改造の記録(葉っぱ♪の水あそび)
参考コトブキ プロフィットフィルターコンパクト改(kusaのブログ。)
小型水草水槽立ち上げ記録シリーズの次回の記事では、水草を育てる際には欠かせないCO2(二酸化炭素)の添加について解説します。
連載「小型水草水槽の作り方」
- 小型水草水槽の立ち上げ!水槽の選び方とセッティング方法を解説!
- 小型水槽におすすめ!外掛け式フィルター改造で濾過能力向上
- 水草水槽には欠かせない!発酵式でCO2を添加する方法
- 小型水草水槽の立ち上げ!購入する水草の種類を決める方法
- 小型水草水槽の立ち上げ!設置場所からろ過までコレで完璧!
CO2の添加方法は大型ボンベを使う方法、小型ボンベを使う方法など何通りかありますが、その中でも最も手軽な発酵式について説明します。次回もぜひ読んで下さいね!