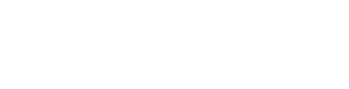亀を飼い始めて一番最初に悩むことって何でしょうか。どんな飼育ケージを使うか? それもあるかもしれません。でも同じようなタイミングで、これから毎日何を食べさせていくのかということも考えますよね。
そんな時の参考になるように、私が使ったことのある亀のエサを色々と紹介してみることにしました。飼育歴の長い人でもいつも同じエサを使っている場合もあるので、実はあまり多くの餌のことを知らないということもあるかもしれません。何かのお役に立てば幸いですし、私が使ったことのない餌を使っている人にはぜひ使用感など教えてもらいたいです。
今回は亀のエサ紹介の第1弾として、まずは水棲亀のエサでは定番中の定番であるテトラ レプトミンを紹介します。ちなみに餌よりも飼育ケージの方が気になる!という方や、餌だけでなく亀の飼育全体のことが知りたいという方は、以下の亀の飼い方をまとめたページを参考にして下さい。
-

-
亀の飼い方・飼育方法-水槽から紫外線・ろ過まで完全まとめ
亀の飼い方として、屋内飼育(特に水槽飼育)における必要なもの・ろ過・セッティング例・普段の世話などを解説しています。飼育ケース・エサ・紫外線ライトなどの商品例も挙げながら、亀を飼うための環境作りの方法を詳細に紹介します。
テトラ レプトミンとは
「テトラ レプトミン」とは、ドイツのアクアリウム用品などを手がける業界きっての有名企業・テトラ社が製造しているカメ用(水棲亀用)の配合飼料です。亀を飼っている人ならば一度は名前を聞いたことがあるんじゃないでしょうか。
以前私が飼育している亀を動物病院に連れて行った時、獣医さんに「餌は何あげてます?レプトミンですか?」みたいな感じで訊かれるくらいメジャーな亀のエサです。
本体側面の説明書きによると、レプトミンは亀の成長に必要な栄養素をすべて配合したバランス栄養食で消化吸収にも優れるそうです。カルシウム(Ca)とリン(P)がバランス良く含まれており、甲羅を丈夫に保つことができるとも書いてあります(ちなみに水棲亀に最適なカルシウム・リン比は、 Ca : P = 2~3 : 1と言われています)。
レプトミンの栄養バランスの良さには定評があり、これだけ食べさせておけば大丈夫というブリーダーもいるとか。世界中で利用されており歴史も長い商品なので、信頼性の高さはピカイチです。
レプトミンは2016年頃にリニューアルされ、以前のものとはパッケージ、バリエーション、栄養バランス等が少し変わっています。
成分
保証されている成分は以下の通りです。
| 粗蛋白質 | 37.0%以上 |
|---|---|
| 粗脂肪 | 4.5%以上 |
| 粗繊維 | 2.5%以下 |
| 粗灰分 | 15.0%以下 |
| 水分 | 9.0%以下 |
それぞれの成分について簡単に説明します。
粗蛋白質はアミノ酸やアンモニアも含んだ大雑把なタンパク質の量のことで、粗脂肪は飼料中の脂溶性物質のことです。粗脂肪のには脂肪の他にろうなども含まれます。また粗繊維は腸内環境を整えると言われるセルロースにその他の糖などを合わせた量で、粗灰分は飼料中のおおよそのミネラルの量のことです。水分は文字通りですが、この水分が少ない方が腐敗しにいエサとなります。
それぞれに「粗」とついているのは、厳密な量を測るのが難しいため大体の値を示しているからです。生餌などをあたえると栄養分の管理が難しくなりますが、レプトミンのような配合飼料では成分が保証されているので管理しやすいです。
他に特徴的なものとして、ビオチンをはじめとしたビタミン類、魚に多く含まれるオメガ3脂肪酸(いわゆるDHA)、免疫力を高めるβグルカンなども配合されています。
-

-
亀のエサの種類とおすすめ!あげ方や食べない時の対処も解説
亀の飼育で重要な亀のエサについてまとめます。爬虫類に必要な栄養素とバランス、配合飼料・生き餌・乾燥餌などのエサの種類、与えてはいけないエサ、エサの与え方等を解説します。亀以外にトカゲ・ヤモリ・ヘビ等の飼育にも役立ちます。
亀の餌の種類や、亀が必要としている栄養素についてもう少し詳しく知りたいという方は、こちらの記事も読んでみて下さい。配合飼料だけでなく、生き餌や乾燥飼料、エサの与え方、与えてはいけないエサ、栄養補助のためのサプリメントなどかなり幅広い内容について解説しています。
原材料
こちらも説明書きによると以下のようになっています。
野菜類、フィッシュミール、植物性蛋白質、酵母、オキアミミール、油脂、藻類、ビタミン類、ミネラル類、レシチン、β-グルカン
野菜類が多いのが特徴的です。植物質の原材料を入れて栄養バランスを向上させようとしているのが伺えます。レプトミンの緑っぽい色はここら辺の植物由来のものかもしれませんね。
えさの与え方
1日最低2~3回、数分で食べ尽くす量を与えるようにとのことです。ただ、これは子亀の時の基準ではないでしょうか。ある程度成長したカメにこんな量を与えていたらすぐにぶくぶくに太ってしまいそうです。甲長10cm以上のカメ用サイズの商品の説明書きにもこんな感じに書いてあるのは少し不思議ですね。
私が飼育している亀は大体2歳のニホンイシガメ雄ですが、餌は2日に一回程度にしています。私の飼い方では基本的に冬眠させないため、太りすぎないように心がけています。しかしやや気にし過ぎな気もするので、セミアダルト~アダルトの亀には1~2日に1回程度の給餌が標準的な量ではないかと思います。
ラインナップ

レプトミンは関連商品の数がもともと多かったんですが、2016年のリニューアルでバリエーションがさらに増えました。どのような商品があるのかを紹介していきましょう。
まず、レプトミンの最もスタンダードな商品が、「レプトミン スティック」と呼ばれる甲長10cm以上の亀を対象に作られた商品です。甲長10cm以上の亀が食べやすいサイズとなるよう、粒の大きさが13~18mm程度に調節されています。レプトミン スティックには、容量の異なる5種類(20g/50g/110g/225g/500g)のラインナップが存在しています。
ちなみに、テトラ創立60周年(2014年か2015年頃)の時には上の画像のような20%増量タイプが同じ値段で販売されておりなかなかお得でした。こういうサービス精神は嬉しいですね。今後もこのように期間限定のラインナップが登場する可能性はあるでしょう。
バリエーション
レプトミンの商品バリエーションとしては、子亀用の「テトラ レプトミン ベビー」、成長期の亀用の「テトラ レプトミン ジュニア」、特に大きな亀用の「テトラ レプトミン ジャンボ」、そして嗜好性バツグンの「テトラ レプトミン スーパー」があります。
レプトミン ベビー
レプトミン ベビーは、甲長5cm未満の子亀・稚亀用の配合飼料です。成長途中の亀に与えることを前提としており、レプトミン スティックとは栄養素の配合割合が多少異なっています。
具体的には、身体を作るために重要な「たんぱく質/脂肪」や骨格形成に強く影響する「カルシウム/ビタミンD3」を多く含んでいます。また、「フィッシュミール/シュリンプ」を強化配合しており、肉食傾向の強い子亀好みの味付け担っています。
粒の大きさは2~3mmと子亀にも食べやすいサイズになっています。内容量が42gと110gの2つのラインナップが用意されています。
レプトミン ジュニア
レプトミン ジュニアは、甲長5~10cmの育ち盛りの亀向けのバリエーションです。こちらも成長途中の亀に与える前提であるため、栄養配分はレプトミン ベビーとおなじになっています。粒の大きさは8~10mm、内容量は32gと82gの2種類が用意されています。
レプトミン ジャンボ
レプトミン ジャンボは、レプトミン スティックが対象としている甲長10cm以上の亀よりも、さらに大型の亀用に用意されているバリエーションです。粒の大きさは20~24mmで、レプトミン スティックの1.3~1.5倍程度の大きさになっています。
栄養素の配合バランスは、レプトミン スティックと同じになっています。220gと500gの2種類のラインナップが用意されています。
レプトミン スーパー
レプトミン スーパーの方は成分も通常のレプトミンとはだいぶ異なり、亀の好物であるエビなどを多く配合することで嗜好性を高めています。それにより偏食傾向の強い亀や、飼育を開始直後の警戒心が強くなっている亀も食いつきやすい餌になっています。
「小さなスティックタイプ」と「大きなスティックタイプ」の2種類が存在し、小さなスティックタイプは内容量85gと170gの2種類、大きなスティックタイプは内容量310gの商品が用意されています。
-

-
ちょっとリッチな亀のエサ!レプトミン スーパーを分析!
水棲亀のエサの中でもかなり高価な部類に入る、テトラ レプトミン スーパーを紹介します。亀の好物のエビや魚など動物質原料を多く配合して嗜好性が高いため、状態が良くない、食欲減退中、まだ餌付いていない亀などに適したエサです。
レプトミンスーパーについては個別に解説した記事もあるので、ぜひこちらも読んでみて下さい。嗜好性が高いだけでなく、色揚げ効果(体色が綺麗になる効果)があるとも言われています。
レプトミンの使用感・レビュー
レプトミンについて解説したところで、私が実際にレプトミンを使用した際の使用感を交え、テトラ レプトミンというエサのレビューをしたいと思います。
絶大な安心感
やはり有名で信頼性が高いエサなのでこれを使っていると安心感があります。今のところレプトミンが原因のトラブルなどはありません。
もしカメが病気になったりしても、原因としてエサをまず外せるというのは原因解明に大きく役立ちます。そういった意味でやはり安心感がある餌ですね。
嗜好性はそこそこ
ウチではレプトミン以外の餌も色々と試していますが、他の餌に比べるとやや食いつきに劣るかなという印象があります。決して食べないということはありませんが、レプトミン スーパーやレバーなんかを与えると本当に激しく餌の追加を求めてくるのに対し、普通のレプトミンだとそこまで激しい行動はとらないですね。
レプトミンスーパーやレバー以外の、特に嗜好性が高いわけではない普通の配合飼料にも、レプトミンよりも食いつきが良い餌は多くあります。また、長期間与えているとレプトミンに対する飽きがくることもあるようです(他の餌も同様だと思いますが)。やはり動物質のエサの方が食い付きが良いので、植物質を多く含むレプトミンは嗜好性という点では劣りがちなのかも知れません。
こんな時に使いたい!
亀の日常的な主食にすることをおすすめします。これをベース飼料として与えながら、時々違う餌も与えて亀の食欲を保つのがいいのではないでしょうか。ただし嗜好性の高い餌をあげすぎるとレプトミンを食べてくれなくなる可能性があるので注意です。
すこし値段が高めなのが唯一の弱点といったところでしょうか。
亀のエサの定番・テトラ レプトミンのまとめ
レプトミンは昔からあるエサなだけに、実績が多数あり安心感を感じられる亀の餌です。エサの良し悪しを亀に直接確認できない以上、実績があるのはエサ選びの上では非常に大きなポイントになるでしょう。
一方で、K-kiが飼育している亀のように、あまりレプトミンが好きじゃない個体も多いようです。K-kiが飼っているニホンイシガメの場合は、飼い始めてから1~2年はレプトミンを食べていましたが、だんだん飽きてしまって食べなくなったので、今は別の餌を与えています。
嗜好性があまり高くないという弱点を補えるように、他の餌と組み合わせて与え、できるだけ長期にわたって亀が食べてくれるような工夫をするのが良いと思います!
今回は亀の餌の定番中の定番であるテトラ レプトミンを紹介しました。いつも使っているえさでもこうして詳しく調べてみることで分かることもありますね。私にとっても勉強になりました。今後はまた違う種類の餌のレビューもしていく予定です!